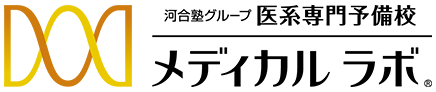メディカルラボ通信
2025年6月号『医学部を目指すための学習アドバイス’25~生物編~』
●
2021年度から実施された大学入試共通テスト(以下,共通テスト)は今回が5回目となりました。
2025年度の私立医学部の入試問題ですが,久留米大学のように大幅に難化した大学もありましたが,現在判明している範囲では特に大きな変化は見られない大学が多い印象です。
2025.6.30 公開
近畿地方では平年より22日も早く史上最速で梅雨明けしました。全国的にはもう少し雨の日々が続くかと思われますが,体調など崩していないでしょうか。
気圧が下がると頭痛を始めとして体調不良を引き起こしやすいそうです。温めのお風呂にゆっくりと浸かることでリフレッシュするのも良いかもしれません。
さて今回は,メディカルラボの生物講師の小川直秀先生に,25年度入試の傾向を踏まえ,医学部を目指す上で必要な生物の学習ポイントについてアドバイスをいただきました。
気圧が下がると頭痛を始めとして体調不良を引き起こしやすいそうです。温めのお風呂にゆっくりと浸かることでリフレッシュするのも良いかもしれません。
さて今回は,メディカルラボの生物講師の小川直秀先生に,25年度入試の傾向を踏まえ,医学部を目指す上で必要な生物の学習ポイントについてアドバイスをいただきました。
CONTENTS
大学入学共通テストの出題傾向
2021年度から実施された大学入試共通テスト(以下,共通テスト)は今回が5回目となりました。
まずはこの5回の平均点を見てみましょう。初回の2021年度(第1日程)は72.64点と理科②の中で最も高かったのですが,2回目の2022年度は48.81点と大きく低下しました。3回目となる2023年度はさらに低下し,得点調整実施後で48.46点と理科②の中で最も低くなりました。その翌年の2024年度は54.82点となり,前年度の得点調整実施後の得点から6.36点上昇しました。そして,新課程入試初年度となる5回目,2025年度は52.21点で,前年度並みの平均点になりました。
次に内容を見てみます。初回の共通テスト(2021年度)は,教科書で扱われていないようなテーマが多く扱われたこともあり,問題文を読むだけで正答にたどりつけるような問題が多く見られました。その結果,平均点が近年にないほど高くなりました。しかし,翌年の2回目(2022年度)は「思考力,判断力,表現力等を発揮して解くことが求められる問題」を重視する傾向が極端に高まり,解答に際して知識と複数のデータを組み合わせる問題が増加しました。そのため分量が増加し,平均点の大幅な低下につながったと考えられます。さらに,2023年度(3回目)は,これまで以上に問題文が長くなって図や表も増えたため,与えられた情報が多くなり,高度な読解力,思考力,分析力など必要とする問題になりました。その結果,平均点は2回目よりさらに低下し,選択科目間のバランスをとるための得点調整が実施されるに至りました。その翌年,2024年度(4回目)は,前年度とは異なり,教科書の内容を中心とした比較的平易な知識問題が増加しました。また,実験の設定の読み取りが困難な問題や複雑なデータ処理を必要とする問題が減少し,さらに問題の分量も減少したため,受験生にとって全体的に取り組みやすい問題になりました。そして,2025年度(5回目)は,大問数が今までの6題から1題減って5題になりました。それに伴って1問当たりの情報量や設問文の分量が増加し,これによって読解量と処理能力が問われる内容が多くなりました。特に,仮説を立ててデータからその正誤を判定する実験考察問題が多数を占めました。
したがって,大問数は減ったものの思考力重視の設問が増えたことで,難度は2024年度と同程度だったと言えます。
2025年度の共通テスト「生物」は,知識を使いこなす力,そして資料から適切な判断を導く能力を,バランスよく問う構成となっていました。今後の共通テストでもこの傾向は継続・強化されると予想され,学校教育における「主体的・対話的で深い学び」の重要性がますます高まっています。受験生の皆さんは日頃から「なぜそうなるのか」「他の事象とどうつながるのか」を考える姿勢をもって学習に取り組むことが,得点力の向上につながってくると言えます。
私立医学部の出題傾向
2025年度の私立医学部の入試問題ですが,久留米大学のように大幅に難化した大学もありましたが,現在判明している範囲では特に大きな変化は見られない大学が多い印象です。
近年の流れになっていますが,杏林大学や埼玉医科大学のように,実験考察問題の出来不出来で大きく差がつきそうな大学が増えた印象があります。新課程における学習内容の変化による影響が出ているのかもしれませんが,実験考察問題が苦手な受験生は十分な対策が必要です。
また,酸素解離曲線や細胞接着,モータータンパク質などのように,新課程では一部の教科書にしか掲載されなくなった分野も相変わらず出題されています。自分が使っている教科書に掲載されていなくても,他社の教科書に載っていれば出題される可能性があります。学校の先生や予備校の講師などにどの内容を学習しておくべきか聞いてみるといいでしょう。
国公立医学部(2次試験)の出題傾向
2025年度の国公立医学部の入試問題ですが,現在判明している範囲では,東京大学や京都大学,名古屋大学のように全体的に論述量が減少している大学が多い印象ですが,それほど難度は低下していないことに注意が必要です。その要因としては,実験の設定の読み取りづらかったり,複雑なデータ処理を必要としたりするなど,高度な思考力が要求される実験考察問題が増加していることが上げられます。 また,ここ2年ほど30ページを超える分量の問題が出題されていた東京大学ですが,2025年度はやや減少して28ページでした。他大学でも,京都大学は24ページ,大阪大学は20ページというように,国公立大学では入試問題のページ数が多くなる傾向が見られます。赤本などの過去問集では編集の都合上,実際のページ数とは異なる場合も多いので,実際の入試問題を大学のWebサイトでダウンロードしたり,塾や予備校で集めている問題を見せてもらったりして,ページ数も含めた,問題全体の雰囲気を掴んでおくことをおススメします。